はじめに
僕が「シスアドが世界を支配するとき」の執筆を開始したのは2005年7月6日だった。そのころクラリオンワークショップで講師を勤めてた。 その次の日、ロンドンで地下鉄とバスが爆破された。 爆破されたバスには僕が毎朝仕事に行くのに使ってるのもあった。 幸運にもその日、僕はクラリオンワークショップに呼ばれてミシガン州にいて助かった。 作家でなくてもこの幸運を奇妙に思うだろう。 僕はショックでこの話の執筆を数ヵ月間進めることができなくなった。
執筆にもどると、世界がオフラインになりつつある中でサーバをオンラインにし続けようと得意気に奮闘するフィリックスとヴァンの話に俄然やる気がでてきた。 一度作られたキョーレツな不安は消すことができない。 僕なんか80年代の核戦争の不安があって、Y2K、気候変動みたいな空想上の不安なか大きくなった。 この話も世界にふりかかる危機の話だ。
僕自身、若いころシスアドだった。 今でもシスアドの仕事に敬意を持ってる。 シスアドは秘密の世界の管理者で、僕らの生活を支えてくれてるんだ。
- クラリオンワークショップ SF作家志望のためのワークショップ
本文
一章
午前2時、フェリックスの仕事用の携帯電話が鳴った。
「どうして寝る前に電源を切っておこないのよ。」 ケリーは寝返りをうち、いらだたしげに彼の肩をこづいた。
「電話がかかってくるからだよ。」
ケリーはベッドサイドで寝る前に床に脱ぎ捨てておいたズボンを履いている彼をけりながら言った。
「医者でもなにのに。」
「シスアドなんて最悪。」
「それが仕事なんだよ。」
フェリックスは言った。
「公務員かなんかのようにこき使って...。あなたはもうパパなのよ。真夜中に誰かさんがアダルトサイトを見れなくったって放っておけばいいじゃない。切って。」
フェリックスは正論だと思ったが、携帯に出た。
「メインルータガハンノウシマセン。BGPニハンノウシマセン。」
合成音声が答えた。 フェリックスはわざと悪態をつき、嫌な気分をまぎらわせた。
フェリックスはケリーに言った。 「家から直せるかもしれないよ。」 彼はラックのUPSにログインしてルータをリブートできた。 UPSは異なるネットワークセグメントにあり、そのUPSで電源供給している独立したルータを使っている。
ケリーはベットのヘッドボードにもたれ体を起こしているようだった。
「私と一緒になって5年、一度も家から直したことないじゃない。」
彼女は知らなかった。 フィリックスはいつも問題を解決していたけれでも、そのことを彼女に伝えていなかった。 今回は彼女の言うとおりだった。 午前1時からログを見るかぎり、データセンターのケージへ出かけるほかなかった。
統一無限いじわる法則。フィリックスの法則だ。
5分後、フィリックスはハンドルを握っていた。 彼は家からでは問題を解決できなかった。 問題のネットワークセグメントのルータが死んでいる。。 最後に同じような問題が起こったのは、バカな作業員がデータセンターへ通じるメインの配管を地下作業車でぶち抜いた時だ。 その時はフィリックスも工事用の穴の上で、一週間24時間、復旧しようと1万本のワイヤーをつなげ直している工事業者をののしった50人の怒れるシスアドの一人だった。
携帯が2度鳴った。フィリックスは出力をカーステレオにつないだ。巨大なベーススピーカーが別の重要なネットワークの通信が途絶えたと報告する合成音声を流した。
3度目はケリーだった。
「もしもし。どうしたんだい? 声色が変だけど」
彼は無意識にほほえんだ。「冗談はよしてくれよ。」
「愛してるわ。フィリックス」
「僕もだよ、ケリー。さあ、寝なきゃ。」
「2.0が起きてるの。」
フィリックスとケリーは、彼らの赤ちゃんを2.0と呼んでいた。 子宮でベータテストされ、ケリーが破水したとき、 連絡を受けたフィリックスは「正規版がリリースしたんだ」と騒ぎながら職場からかけつけた。 赤ちゃんが初めて泣き止む前には、彼らは彼を2.0と呼びはじめていた。
「この子はおっぱいを吸うために生まれてきたんだ。」
「起こしちゃったんだね。」
彼はデータセンターに着くところだった。 午前2時に行き交う車は無い。 彼は車の速度を緩め、駐車場への入口に入る前に路肩によせた。 地下の駐車場へ入って、電話を切りたくなかった。
「私を起こしたわけではないわ。」
「7年間勤めてるんだもの。3人の部下がいるんでしょ。彼らに電話してまかせましょう? あなたはよく働いてるわ。」
「自分が何もやってないことについての報告書なんて読めないよ。」
「そうね。」
「お願い。夜中に一人で起きているのは嫌だわ。帰ってきて。」
「ケリー...」
「怒ってももなんにもならないのはわかってるの。ただ、あなたに一緒にいてほしいのよ。あなたといっしょに寝るといい夢が見られるの。」
「わかったよ。」
「簡単でしょ?」
「ああ、簡単だ。きみは一人で悪い夢は見ないよ。そして、僕は僕の仕事をする。これから電話して休暇を取るよ。」
「シスアドに休暇なんてないわ。」
「かならずそうすよ。約束する。」
「素敵。」彼女は喜んだ。
「あらやだ。2.0が私のバスローブにコアダンプを吐いちゃったわ。」
「赤ちゃんが?」
「そうなの。」
彼女が電話を切ったので、フィリックスは車を駐車場へ入れ、入館認証へ向かった。 眠気が残った眼球がちょっとでも良くみえるように、目を見開いて網膜スキャンをおこなった。
彼は立ち止まり、 He stopped at the machine to get himself a guarana/medafonil power-bar and a cup of lethal robot-coffee in a spill-proof clean-room sippy-cup. 彼は荒々しく、バーをはねのけ、コーヒーを一口すすった。そして内側のドアが彼の手の起伏を読み取り、彼を計測した。シューという音と共にドアは開き、エアロックの気圧差で彼は聖域に押し出された。
まるで精神病院だった。それぞれのラックは2から3人のシステム管理者が同時に作戦を実行できるように設計されていた。四角く区切られたパーティションはうなるサーバとルーター、ドライバーで一部の隙もなく、20人ものシステム管理者で息がつまりそうだった。システム管理者のスタイルは理解不能のスローガンが描かれた黒いTシャツと携帯電話と多機能工具をベルトに装着するのが定番だ。
通常、サーバールームは寒いぐらいだが、閉ざされた小さな空間にこの人数で、暑かった。 フィリックスが通り過ぎると、5、6人が顔をしかめた。 2人は彼に名前であいさつした。
「フィリックス」ヴァンが呼んだ。ヴァンは今日、電話番ではなかった。
「どうしたんだよ。明日ボロボロになるのは一人だけでいいだろうに。」フィリックスは言った。
「どうしたんだよって...。俺のがそれなんだ。1時半ごろに落っこちて、プロセス・モニターで起こされた。俺が行くってお前に電話しとけばよかったな。そうすりゃ、お前が出場ってくる必要はなかった。」
友達5人と借りているフィリックスのサーバは一階下のラックだった。 フィリックスはこのサーバもオフラインなのか心配だった。
「何がおこってるんだ?」
「ワームだよ。どっかのマヌケ管理してたWindowsがゼロデイアタックを受けて、ネットワーク上のIP全てにモンテカルロ法で探査してんのさ。しかもIPV6も。基幹シスコの管理インターフェースがIPV6だろ。おまけに10以上の同時探査を受けると通信を受付けなくなるんだぜ。で、すべてのネットワーク間通信がおじゃんてわけだ。さらにだ。DNSも調子おかしい。昨日の夜、だれかがゾーン転送をダメにしたみたいだし。そうだ。お前のアドレスブックにある全てのアドレスに送信されたメールとIM componentあったんだ。そのメールがアーカイブされてたメールのトロイの木馬を召喚するエリザの呪文を吐きやがったんだ。
「最悪。」
「まったく。」ヴァンは2番めのタイプのシスアドだ。伸長は180センチ。ポニーテールでbobbing Adam's apple。Tシャツの薄っぺらな胸には“CHOOSE YOUR WEAPON”(武器をとれ?)に多角形のロールプレイングゲームのサイコロがプリントしてある。
フィリックスは1番めのタイプのシスアドだった。平均より7、80ポンドほど体重があったが、整えられた鬚が顎をおおている。彼のTシャツには“ハロー クトゥルーHELLO CTHULHU”とあり、口のないかわいいハローキティ調のクトゥルーがプリントされていた。ヴァンとの付き合いはかれこれ15年になる。Usenetで知り合って、トロントのFreenetの飲み会のf2f、スタートレックコンベンションで1、2回実際に会って、フィリックスはアーデントで彼を雇う関係になっていた。ヴァンは信頼でき、几帳面だった。電気技士として経験を積んでいて、日付時間ごとに自分がおこなった作業のすべてをノートに記録していた。
「今回のはレイヤー8の問題ってわけじゃないな。」ヴァンが言った。実際に問題が起きていた。添付ファイルのトロイの木馬は過去の遺物だった。誰も怪しげな添付ファイルなど開けなくなっていたからだ。しかし、Ciscoを喰い尽くすワームは経験不足の技術者のせいだった。
「またマイクロソフトか。午前2時に出てくるといつもレイヤー8か、ものぐさマイクロソフトの問題だ。」
第二
結局、彼らはインターネットからルータを切り離した。 もちろん、フィリックスがその作業をおこなったわけではなかった。 でも、フィリックスも同じようにIPV6のインターフェースを無効にして、リブートしたいとは思っていた. 切り離したのはa couple bull-goose Bastard Operators From Hellだった。 彼らは核ミサイルの格納庫を開けるように同時に2つのキーを廻さなければならなかった。
フィリックスとヴァンはすぐにArdentを復旧した。 インターネット上の全てのマシンがワームに汚染されて、新たに感染しているようだった。 フィリックスは数百回のタイムアウトの後、なんとかNISTとBugtraqにアクセスして、ワーム対策のカーネルパッチをダウンロードしてマシンに適用した。 午前10時になろうとしていた。 he was hungry enough to eat the ass out of a dead bear,ほど空腹だったが、カーネルを再構築し、再起動して復旧した。 ヴァンのの長い指は管理コンソールのキーボードの上で舞い、彼の舌はそれぞれマシンの負荷状況を表示させるたびにつき出ていた。
「Greedoは200日間の連続稼働中だったのに...。」 Greedoは彼らがスターウォーズの登場人物にちなんで名付けたラックで最古参のマシンだった。 彼らはスマーフからマシンの名前をつけていて、スマーフが思いつかなくなると、マクドナルドにちなんだ名前をヴァンのノートから付けはじめていた。
「また記録はつくれるよ。」フィリックスは言った。 「下の階に5年以上の連続稼働中の486があるけど、再起動しなくちゃならないなんて...。」
「486機って何につかってんの?」
「別に。5年間連続稼働中なんだ。まるでおばあちゃんを安楽死させるような気分だよ。」
「腹へったな。」ヴァンが言った。
「そうだな。」フィリックスは言った。 「お前のマシンを起動させて、で、俺の。そのあとレイクビューへ朝飯のピザ食ったら、あとは今日は休みだ。」
「出てくれるの」ヴァンが言った。 「文句の言いようもないよ。上司って言えば、職場でこき使うもんだろ。それが、こんなに寛大だなんて。」
第三
「電話だよ」ヴァンが言った。 フィリックスは486から出てきた。 電源が入らなかったので、スパムの対処に追われている他のシスアドから予備電源を借りて、取り付けていたのだ。 マシンの裏での作業中に体をひねった際ベルトから落とした携帯をヴァンに拾ってもらい、電話に出た。
「もしもし、ケリー?」 様子がおかしたかった。鼻をすする音が聞こえた。 2.0がバスルームで遊んでいるのか? 「ケリー?」
回線が切れた。 かけ直したが、呼出音もならないし、音声応答もない。 彼の携帯はタイムアウトし、NETWORK ERRORを表示していた。
「どしたってんだ。」彼は当惑して言った。 携帯電話をベルトに戻した。 きっと帰りがいつになるか聞きたかったのか、何か買って帰ってほしいてことだろう。 彼は留守電にメッセージを残してくれるだろうと思った。
もう一度、携帯が鳴ったときにはフィリックスは電源供給をテストしていた。 携帯をもぎとると、彼は言った。 「ケリー。どうしたんだ?」 彼は声に苛立ちがでないようにした。 彼は罪の意識を感じていた。 技術的に言えば、Ardent Financial LLCの責任から開放され、サーバもオンラインに復帰していた。 この3時間は、会社に請求しようと考えていたが、まったく個人的なことだった。
咽び泣く声が聞こえた。
「ケリー?」 フィリックスは顔から血の気が引き、指先の感覚が無くなるのがわかった。
「フィリックス.....あの子が、あの子が...死んじゃう」 咽び泣きの中、なんとか聞き取ることができた。
「ケリー? 誰のことなんだ?」
「ウィル..」
「ウィル? って...」彼はひざまづいた。 ウィリアムはフィリックスとケリーが出生届けに記入した名前だった。 フィリックスは声にならない叫びをあげた。
「わたしも体がおかしいわ。立ってられない。フィリックス、愛してるわ。」
「ケリー? どうしたんだ。」
「みんな、みんな....テレビはもう2つの放送局しか映らないわ...外は「死霊のえじき」みたい...」 吐く音が聞こえた。 電話機が壊れかけているようだった。受話器を拭う音がエコーがかかって聞こえた。
「そこでじっとしてるんだ。ケリー」電話が切れる直前に彼は叫んだ。 911に電話したが通話ボタンを押すと同時にNETWORK ERRORが表示された。
彼はMayor McCheeseをヴァンから奪い、486へ繋いだ。そしてコマンドラインからファイアーフォックスを起動して、Metro Policeのサイトを検索した。すぐにインターネットでのアクセスフォームを見つけた。フェリックスはこれまでこれほど混乱したことはなかった。彼はこれまで多くの問題を解決して来ていたし、解けない問題に熱狂していた。
フェリックスはアクセスフォームにバグレポートを書くようにケリーとの会話の詳細を書き込んだ。タイピングスピードは恐ろしく速く、記述は完璧だった。そして、送信ボタンを押した。
ヴァンは肩越しに覗き込んでいた。「フィリックス...」
「ちくしょー」フェリックスが叫んだ。彼はラックの床に座っており、ゆっくりと立ち上がった。ヴァンがノートを取り上げ、いくつかのニュースサイトを見てみたが、全てタイムアウトを起こした。言いようのないひどいことが起こっているようだった。強力なワームがネットワークに影響を及ぼしているのかもしれなかった。
「帰らなくちゃ」フェリックスが言った。
「俺が送ってく。お前はとにかく奥さんに電話し続けろ。」ヴァンが答えた。
彼らはエレベータへ向かった。建物の数少ない窓の一つがそこにあった。分厚く、頑丈にできた窓だった。彼らはその窓を覗きながらエレベータが来るのを待った。水曜日にしては車は少なかった。警察車両が多かった。
「ウソだろっ?」ヴァンが指さしながら言った。
CNタワーの巨大な象牙のような建物が彼らの西側にぼんやり見えた。まるで砂に差した枝のように塔は傾いていた。そしてゆっくりと傾きつつあった。そのスピードは増し、北東の金融地区へ倒れた。数秒後、塔の先端部分が雪崩落ち、崩れた。ショックに打ちのめされた2人に、塔が倒壊した音が聞こえてきた。粉塵が舞い上がり、世界で最も高い建物がビルを次々と倒しながら雷よりも大きな音を轟かせた。
「放送センターが倒壊した。」ヴァンが言った。CBCの放送塔はスローモーションで崩れていった。逃げまどう人々は落ちてくる石材につぶされていた。窓から見える映像はまるでbitorrentからダウンロードできる良くできたCGのようだった。
他のシスアド達もフィリックスとヴァンのもとに集まって、倒壊を見ようと押し合った。
「何が起こったんだ?」
「CNタワーが倒れたんだ。」フィリックスは自分の声が遠くに聞こえた。
「ウィルスかも。」
「ワーム? 何で?」フィリックスは発言者を見た。彼は若いシスアドで、比較的背が低く、小太りでタイプ2といったところだった。
「ワームじゃないよ。この街全体がウィルスのせいで隔離されてるってメールがあったんだよ。生物兵器だって。」彼はフィリックスに自分のブラックベリーを渡した。
フィリックスは夢中でカナダ保健省から転送されてた予備レポートを読んだ。室内の全ての照明が落ちたのにも気がつかず、読み終えると、ブラックベリーをもとの持ち主へ返した。涙が瞳からこぼれ落ちた。
第四
少しすると発電機が起動した。シスアド達は非常階段へなだれ込んだ。フィリックスはヴァンの腕をつかむと、他のシスアド達と行くのを押しとどめ、言った。
「ここにとどまるべきかもしれない。」
「ケリーはどうすんだよ。」
フィリックスは全てを投げ出しているような気がした。「ケ−ジの中に戻るんだ。ケ−ジは分子レベルのエアーフィルタが設置してある。」
フィリックスとヴァンは上の階の比較的大きなケ−ジの中へ入った。彼らは中に入り、扉を閉めた。背後でシューという音と共に、隔離されるのがわかった。
「でも、おまえ家に帰らないと...」
「生物兵器だ。オーダーメードのスーパーバグ。ここなら生き延びることができる。ウィルスがフィルタを通さなければ。」
「え?」
「IRCへアクセスしよう。」フィリックスは言った。
ヴァンはMayor McCheese、フィリックスはSmurfetteでIRCへアクセスした。チャットのチャンネルはスキップして、ある有名なハンドルを探した。
> ペンタゴン消失/ホワイトハウスも同じく
> サンディエゴではお隣りさんが血反吐を吐いてる。
> 誰かがthe Gherkinをノックしてる。銀行員達がCityからネズミみたいに逃げ出してる。
> 銀座が火事って聞いた。
フィリックスは次のように入力した。 「トロントにいる。みんながCNタワーが倒壊したのを目撃した。生物兵器の噂が流れてる。発症が異常に早い。」
内容を読むとヴァンが言った。 「フィリックス。発症は自分の目でみたわけじゃないだろ。3日前からウィルスに晒された可能性だってある。」
フィリックスは目を閉じて言った。 「もし、ウィルスに晒されて感染しているなら、なんらかの症状があらわれてるよ。」
> > Looks like an EMP took out Hong Kong and maybe Paris—realtime sat footage shows them completely dark, and all netblocks there aren't routing
> トロントにいる人?
あまり見慣れたハンドル名ではなかった。
> ああ。フロント・ストリートだ。
> 僕の妹がトロント大学なんだけど、連絡とれないんだ。連絡とれるかな?
> 電話は今通じない。
フィリックスはタイプすると「NETWORK PROBLEMS」の表示を見た。
「今、思い出したんだけど、Mayor McCheeseってホストでソフトフォン入ってんだけど...」ヴァンはそう言うと、VOIPソフトを起動した。
フィリックスはヴァンからノートPCを借りて、自宅の電話番号にダイアルした。一度呼出し音がなり、無音。そして、イタリア映画に出てくる救急車のような耳障りな音が鳴りだした。
> 電話は通じない。
フィリックスはもう一度ダイアルした。
彼はヴァンを見上げ、彼の痩せた肩が震えるのを見た。ヴァンが言った。
「どうなってんだ。このまま世界が終わるってーのか!」
第五
およそ一時間後、フィリックスはIRCからなんとか抜け出た。アトランタは火に包まれ、マンハッタンはリンカーンセンターのウェブカメラで見たところ、高温の放射能でメチャクチャだった。イスラム過激派のしわざだと噂が出たが、メッカが煙に包まれ、サウジの王族が王宮から退避したと聞くと、次第におさまっていった。
フィリックスの腕は震え、ヴァンはケ−ジの一番遠い角のほうで泣いていた。 フィリックスは何度も家や警察に電話していたが、ここ20分間つながることはなかった。
彼は階下の彼のマシンにsshでログインし、メールをチェックした。スパム、スパム。スパム。スパムメールの山だった。そして大量の自動生成されたメール。Ardentのケ−ジのIDS(侵入検知システム)からの緊急メッセージだった。
IDSからの緊急のメールを開いて読んだ。ルータに対する強引な探査が繰り返しおこなわれていた。ワームのシグニチャーには一致していなかった。発信元に対してtracerouteを実行し、彼がいる同じ建物の1階下の階のマシンからおこなわれているのがわかった。
彼は攻撃しているマシンいポートスキャンをかけ、1337ポートが開かれており、1337はハッカーの文字変換の慣習から“leet”あるいは“elite”の変換コードだった。このポートはワームが出入りするのに使われているようだった。フィリックスは1337ポートを空けたままにしているバグを探すためにググって、侵入されたサーバのフィンガープリントが原因でダウンがおきているネットワークを隔離し、最後に正常に戻した。
ワームは古くさいものだった。数年前に配布されているパッチを適用しておけば感染するようなものではなかった。No mind. 彼もクライアントを管理しており、そのマシンに自分用のrootアカウントを作成するために使っていた。彼はそのマシンにログインすると、ファイルシステムをチェックした。
ログインしているのは彼だけではなかった。scaredyというユーザがログインしていて、フィリックスはscaredyがどんなプロセスを実行しているのかプロセスモニターでチェックした。そしてscaredyは数百のプロセスを展開して、彼のマシンを含むその他多くのマシンへ探査をかけているを確認した。
彼はチャットを開いた。
> 俺のサーバを探査するのはやめろ。
彼は怒号か謝罪、拒否の反応を待ったが、返ってきた反応は違った。
> フロント・ストリートのデータセンターにいるの?
> ああ。
> よかった。僕が最後の生き残りだと思ってたよ。僕は4階にいる。生物兵器での攻撃が外では行われてるみたいだ。僕はクリーンルームを出たくない。
フィリックスは音を立てて息を吐き出した。
> 君は僕にトレースバックしてほしくってプローブしてたのか?
> ああ。
> なるほどね。
賢い奴だ。
> 僕はもう一人と一緒に6階にいる。
> 何かわかったことあるかい?
フィリックスはIRCのログを添付して、相手が概要を理解するのを待った。ヴァンが立ち上がって急いで近づいてきた。彼の目はガラス玉のようだった。
「ヴァン? おい?」
「しょんべんしたいんだ。」ヴァンが答えた。
「扉は開けられない。ごみ箱にあるMountain Dewの空びんを使えよ。」
「そうする」ヴァンは答えると、ゾンビ見たいにごみ箱のほうに向かっていき、空びんを引出すと、フィリックスに背を向けた。
> 僕はフィリックス。
> ウィル。
一瞬、2.0のことが頭によぎり、フィリックスは胃が裏返るのを感じた。
「フィリックス、俺は外にでなくちゃならないと思ってるんだ。」ヴァンはそう言うと、エアーロックがかかった扉のほうへ歩きだした。フィリックスは慌てて、キーボードを落とし、ヴァンの後に続いた。なんとかフィリックスは扉に到達する前にヴァンを取り抑えることができた。
「ヴァン。俺を見ろ。ヴァン。」ヴァンの目は霞がかかり、焦点があっていなかった。
「行かなくちゃならないんだ。」ヴァンがうつろに言った。「帰って猫に餌をやらなきゃ。」
「外は即効性の強い致死性のヤバいもんが蔓延してる。風で霧散するか、したかもしれないけど、手段がなくなるまで、ここにとどまるしかないんだ。座れ。座るんだ、ヴァン。」
「寒いんだ。フィリックス」
確かに室内の温度は低かった。フィリックスの腕には鳥肌が立ち、足は氷のようになっていた。
「サーバにもたれて座るんだ。排気口近くがいい。少しは温かいはずだ。」彼もラックにもたれ身をかがめた。
> そこにいるか?
> まだいる。考えをまとめてるところだ。
> どのぐらいで外に出られると思う?
> わからない。
その後、長い間キーを打ち込むものはなかった。
第六
フィリックスはMountain Dewのボトルを2度使っていた。ヴァンももう1度。フィリックスはケリーにもう一度ダイアルしていた。Metro Policeのサイトもダウンしたままだった。
フィリックスはサーバによりかかり、ひざを抱え、赤んぼうのように泣いた。
少し後、ヴァンもフィリックスの側に座り、フィリックスの肩に腕を回し抱きしめた。
「みんな死んだんだ。」フィリックスが言った。「ケリー、俺の息子。俺の家族はもういないんだ。」
「まだ、わからないよ。」ヴァンが答えた。
「もう十分わかってるさ、ちくしょー。おしまいだ。そうだろう?」
「あと数時間ここで耐えて、外に出よう。すぐ普段通りの生活に戻れるさ。災害本部がなんとかするって。軍の出動要請もあるだろう。それで万事OKさ。」
フィリックスは肋を痛めていた。彼は2.0が生まれてから、泣いたことはなかった。抱えたひざをより一層抱き抱えた。
そのとき、エアロックが開いた。
シスアド2人が目を大きく見開いて入ってきた。一人は“TALK NERDY TO ME”(オタクっぽく話しかけてね)のTシャツを着て、もう一人はElectronic Frontiers Canadaのポロシャツを着ていた。
TALK NERDYは言った。「来てくれ。俺たちは最上階で集まってるんだ。階段で移動してくれ。」
フィリックスは彼が息を止めていたのがわかった。
「このビル内に感染者が一人でもいれば、みんな感染してしまう。さあ、行ってくれ。最上階で合おう。」TALK NERDYが言った。
「6階にもう一人いる。」フィリックスは立上りながら言った。(4階の間違い?)
「ウィルだろ。わかってる。彼も最上階にいる。」
TALK NERDYは基幹ルータのプラグを抜いたBastard Operators >From Hellの一人だった。フィリックスとヴァンは階段をゆっくりと登っていった。足音が誰もいないホールに木霊した。冷蔵庫のようなケ−ジの中の後では、階段ホールはサウナのようだった。
最上階にはカフェテリアが備えつけられており、トイレもあり、コーヒーと簡単な食べ物の自動販売機もあった。トイレと自動販売機にはシスアドの行列ができていた。誰もお互いの目を見合わそうとはしなかった。フィリックスはウィルを探しながら、自動販売機の列に加わった。
彼はなんとか売り切れ前に数個のスニッカーズとヴァニラコーヒーの特大カップを買うことができた。ヴァンのほうは席を取っていた。購入した食糧をヴァンにあずけてフィリックスはトイレの列に並んだ。フィリックスは持っていたスニッカーズ1つを「持っててくれ」と言いながら、ヴァンに放り投げた。
フィリックスとヴァンが落ち着いたころには、すべての避難は完了し、みんな適度に胃に食糧を詰め込んだところだった。TALK NERDYとその仲間が戻ってきた。彼らが食糧受渡しエリアのレジの現金をかっさらい、TALK NERDYがそれを収めるころには、会話は途絶え、沈黙が拡がっていった。
「私の名前はUri Popovich、でこっちがDiego Rosenbaum。みんな集まってくれてありがとう。わかってることを整理しよう。ビルの電気はここ3時間、発電機でまかなわれてる。視認した限りでは、トロント中心部で電気が通ってるのはここだけだ。電気はあと3日間はもたさなければならないと思う。外では未知の生物兵器が散布され、致死性であり、発症も2、3時間、呼吸するだけで感染する危険がある。従って、これから午前5時まで決して外部への窓は開けないでほしい。私の許可があるまで控えてくれ。」
「世界の主要都市への攻撃は混乱の中での緊急の反応を引き起こした。攻撃は多岐にわたり、電子的、生化学的なもの。あるいは核、通常の爆発物に及び、非常に広範囲で影響を及ぼしている。私はセキュリティエンジニアだが、この種の一連の攻撃は通常日和見主義と見ることができる。グループBが橋を爆破し、グループAが核兵器を使用する。この場合、グループAの攻撃から対象者は逃げることができなくなり、合理的だ。ソウルにおけるオウム真理教のガス散布は地下鉄でおこなわれ、東海岸時間の2時頃、確認できた限りでは最初のものだ。したがって、so it may have been the Archduke that broke the camel's back.これは確実な線で、オウム真理教はこの事件には関わっていない。彼らにはサイバーテロの前歴、また、これほど広範囲にわたる目標を同時に攻撃するのに必要な組織も、技術も確認されていないからだ。基本的にかれらはこんなにスマートじゃない。」
「われわれは先の見えない未来に向けてここで待機している。少なくとも、生物兵器が離散したのを確認するまでは。とにかくネットワークを維持するためにラックに張りつく人間が必要だ。この情報インフラは生命線だ。したがって、サーバの5割は稼働させる必要がある。国家的危機におけるわれわれの責任は倍増する。」
一人のシスアドが手を挙げた。彼は緑色のIncredible Hulk ringTシャツを着て悠然としており、集まったシスアドの中でも最も若かった。
「誰が死んで、あんたを王様にしたの?」
「わたしはここのメインセキュリティーシステムを管理している。ケージの全ての鍵、今現在ロックされている外部への扉のパスワードなんかだ。成り行き上、わたしがこの最上階にみんなを集めて、このミーティングを開いた。わたしは誰がこの役割を誰がやろうと気にかけてはいない。些細なことだ。しかし、だれかがこの役割を引き受けなければならないと思う。」
「正論だね。」若いシスアドが言った。 「でも僕もあなたと同じことならできるよ。僕の名前はウィル・サイロ。」
Popovichは彼を見下ろした。
「それじゃ、君がわたしの話し終わるのを待ってくれたら、君に役割を引き受けてもらうよ。」
「すべて終わったらね。」
ウィル・サイロは背を向けて窓の方へ歩いていった。彼はわざと視線を逸していた。フィリックスの視線はウィルに引きつけられた。そして、街の中心部から黒いガソリンの煙が煙が立ちのぼっているのを見た。
Popovichは気がそがれたようだった。
「さて、われわれはどうすべきだろう。」
彼は言った。
若いシスアドは沈黙をしばらく眺め、言った。
「あれ、もうぼくの番かな?」
悪意のないくすくす笑いが起こった。
「ぼくが思うに、世界はもう終わりなんだよ。必要なインフラには用意周到な攻撃がおこなわれてる。これほど巧妙に攻撃をおこなう方法は一つしかない。インターネットだ。攻撃が日和見主義的だって理論をとるにしても、ぼくらはどうやって数分で日和見主義的攻撃がおこなわれた考えなきゃならない。それがインターネットってわけ。」
「そうすると君はインターネットをシャットダウンすべきだって言うのかい?」Popovichがかすかに笑いながら言いかけたが、ウィル・サイロが何も言わないとわかると黙った。
「ぼくらは昨夜インターネットが死にかけた攻撃を見たろう。基幹ルータにちょっとしたDoS攻撃、ちょっとしたDNSなんとかで牧師の娘さんみたいに落っこっちゃうんだよ。警察や軍は技術恐怖症の根性なしで、結局ほとんどインターネットに依存してない。ぼくらがインターネットを落としたら、部分的にだけど攻撃者を不利にすることができる。ほっといても守備が大変なだけだもんね。それに時間が経てば、やり直すことができるし。」
「君は正気なのか?」
ポポビッチは言った。彼の顎は文字どおり開いたままだ。
「論理的に考えなよ。まったく大事なときにこそ論理的に考えることが必要なのに。こういうのって問題だよね。論理的に考えなきゃ。」
そこここでざわめきが持ちあがり、怒号に変わった。
「静かに!」
ポポビッチが大声で言った。騒ぎは1ワットまでおさまった。ポポビッチはもう一度叫ぶと、床を踏みならした。ようやく見かけ上は落ち着いたようだった。
「1度に1人ずつだ。」
彼は言った。彼は顔を紅潮させ、ポケットに手を突っ込んだ。
あるシスアドは残ることを、また別のものは出ていくことを。 彼らはケージの中で隠れるべきだった。 今あるものの目録をつくり、四つに分けられたグループの各リーダーの割り当てをきめるべきこと。 外へ出て警察か病院のボランティアを見つけるべきこと。 正面入口のセキュリティを確保する要員を決めるべきこと。
フィリックスは自分が手をあげていることに驚いた。ポポビッチが発言に許可を与えた。
「僕の名前はフェリックス・トレモント。」彼はそう言うと、テーブルの上に立ち上がってPDAを取り出した。
「これからみんなに読むから聴いてほしい。」
「工業世界の巨大なくたびれた鉄の体の政府のみなさん。わたしは新しい精神の家、サイバースペースから来ました。未来の代表として、わたしたちは過去のものとしてのあなた方に干渉してほしくない。あなた方はわたしたちに歓迎されてはいない。あなた方はわたしたちのあつまる場所を統治することはできない。」
「わたしたちには選任された統治体制はなく、これからも持つことはない。したがって、個人での自由な発言以上の権限であなた方に発言することはできないけれども、わたしは宣言する。わたしたちがつくった地球規模の公共スペースは本来、あなた方がわたしたちに課そうとしている統治体制から独立している。あなた方にはわたしたちを支配する倫理的権利も、わたしたちへ強制するわたしたちが恐れるような手段もない。」
「政府は本来、その権力を統治されるものの合意から得ている。あなた方はわたしたちのその要請も合意も持ってはいない。わたしたちはあなた方を招待しない。あなた方はわたしたちを知らないし、わたしたちの世界を知らない。サイバースペースはあなた方国境の内側にはない。サイバースペースは公共事業のようにあなた方がつくったとは思わないでほしい。あなた方にはつくることはできない。サイバースペースは自然の営みであり、わたしたちの集合的活動により成長する。」
「サイバースペース独立宣言からだ。12年前に書かれたものだ。ぼくはいままで生きてきて読んだものの中で最も美しいものの一つだと思ってた。ぼくは、ぼくの子供がサイバースペースが自由で、その自由が実際の世界にも影響を及ぼし、肉体をもった世界もより自由になっている世界で大きくなってほしかった。」
彼は大きく息を吸い込むと手の甲で両目をこすった。ヴァンがぎこちなく彼の靴に手を触れた。
彼は咽び泣きを咳とばし、もう一度大きく息を吸った。
「世界中でぼくらみたいな人々がこの建物みたいに集まってる。みんな昨夜のワームのディザスター攻撃を修復しようとした。ぼくらには独立した力、たべもの、水がある。」
「ぼくらにはネットワークがある。悪意ある人が巧妙につかい、善意の人はその使いかたをわからなかったけれど。」
「ぼくらにはネットワークを気に掛け心配する共通した自由の愛がある。ぼくらには今まで世界が見たこともないような最も重要な組織、政府の責任がある。ぼくらは今や世界のなかで一つの政府に近いものだ。ジューネヴはクレーター。ニューヨークのイーストリバーは火災で国連は避難している。」
「この嵐の中で分散サイバースペース共和国に基本的被害はない。ぼくらは不死で怪物的なすばらしい機械、よりよい世界を再構築する可能性を秘めたものの守護者だ。」
「ぼくはこの仕事がなにごとにも替え難い。」
ヴァンは泣いていた。彼だけではなかった。みんな彼を拍手で称賛することはなかったが、わかっていた。みんなが完全な賛嘆の沈黙で迎え1分近くに及んだ。
あざけり無く、ポポビッチが言った。 「どうやって実行に移すべきか?」
第七
ニュースグループはすぐにいっぱいになっていた。新たに公開していたnews.admin.net-abuse.emailグループには、spamと格闘するシスアドがたむろしていた。そこでは、猛攻撃に直面して強固な仲間意識が形成されていた。
新しいグループはalt.november5-disaster.recoveryで.recovery.goverance、.recovery.finance、.recovery.logistic、.recovery.defenseの階層にぶら下がっていた。 Bless the wooly alt. hierarchy and all those who sail in her.
シスアド達がどこからともなくあらわれた。Googleの分散サーバ群はオンラインだった。強烈なクイーン・コングをボスとしてローラーブレードを履いた手下に巨大なデータセンター内のSWAPアウトして死んでいるサーバのリブート・スイッチを押させていた。the PresidioのInternet Archiveはオフラインだったが、アムステルダムのミラーサイトは生きており、DNSでリダイレクトされ通常通り利用できた。Amazonは落ちていた。Paypalは稼働。BloggerとTypepad、Livejournalはすべて稼働していた。そして電子的温かさを求めて恐怖に打ちのめされた生存者が集まり、数百の投稿でいっぱいだった。
Flickrの写真画像のやりとりは大変なものだった。フェリックスは見るのをやめた。台所でウィルスで苦悶に身をヒエログリフのように歪ませた女性と赤ちゃんの写真を見てしまったからだ。彼女達はケリーや2.0に似ていなかったが、彼女達がそうなっていいはずはなかった。フェリックスは震えはじめ、止めることができなかった。
Wikipediaは稼働していたが、負荷のために反応がにぶかった。スパムはなにごともなかったように届いており、ワームはネットワーク上に蔓延していた。
.recovery.logisticsはもっとも活発だった。
> 地区ごとでニュースグループの投票システムを使えるね。
フェリックスにはこのシステムが機能することがわかっていた。ユーズネットのニュースグループは20年間物理的な問題なく利用されてきていた。
> まず地域の代表を選出し、それから代表者による首相を決める。
アメリカ人は大統領を主張していたが、フェリックスはあまりその主張が好きでなかった。あまりに党派主義的に思えたのだ。彼の未来はアメリカの未来ではなかった。アメリカの未来はホワイトハウスと共に消失したのだ。彼はアメリカよりも大きな入れ物を考えていた。
フランステレコムからのフランスのシスアドもいた。EBUのデータセンターはジュネーブが攻撃で破壊された場合に備えたものだったが、フェリックスより英語がうまいゆがんだドイツ人でいっぱいだった。彼らはカナリア諸島の埠頭にいるBBCチームの生き残りとうまくやっていた。
.recovery.logisticsでは多様な英語が使われていた。フェリックスは彼の側で勢いをつけていた。 シスアドなかには避け難いばかげたフレームウォーに長年の経験を生かすものもいた。 また、有効な提案も上がっていた。
驚いたことに、フェリックスがイカレテルと思っているものはいないようだった。
> ぼくはできるだけ早く選挙をすべきだと思うんだ。最短で明日。
> 管理されていることに合意がなきゃ、ちゃんとまとまんないよ。
数秒後、inboxに返信が届いた。
> ばかげたこと言わないでよ。合意済みの管理?
> わたしの考えてるのが間違ってるといいんだけど、あなたが管理されるべきと思ってる人は
> 今ごろ、みんな机の下で食べたものを吐いてるか、戦時中のシェルショックの症状みたいに
> ぼーとなって街なかをうろついてるわ。
クイーンコングは辛辣だ。フェリックスは彼女の発言は的を射ていると考えざるをえなかった。 シスアドに女性は少ない。そしてそのことはある種の本当の悲劇だった。 クイーンコングのような女性を無視するわけにはいかなかった。 彼は新たな管理組織において女性をどう位置付ければいいか見つけようと、ハッキングしていた。 それぞれの地域に女性と男性一人ずつ選任する。
彼はクイーンコングとキーボードでカタカタと激しく議論した。 選挙は次の日に決まった。 彼はそれを見届けるだろう。
第八
「サーバースペース総理大臣? グローバル・データ・ネットワーク最高えらい人とかは? なんか威厳がある感じでかっこよくきこえない? 総理よりいいと思うんだけど」
カフェテリアでのウィルの寝場所はフェリックスのとなりだった。もう片側にはヴァンがいる。 部屋はクソのような臭いがした。 少なくとも1日は風呂に入っていない25人のシスアドが同じ部屋につめこまれているのだ。 中には数日間風呂に入っていないものもいる。
「だまれよ。お前はインターネットをオフラインにしたかったんだろーが。」ヴァンが言った。
「訂正。ぼくはインターネットをオフラインにし・た・いんだ。現在形ね。」
フェリックスは片目をかすかに開けた。とても疲れていた。まるでウェイト・リフティングをしたかのようだった。
「いいかい。ウィル・サイロ君。君がぼくの考えに否定的なら自分の考えを押し進めればいい。ぼくの考えがばかばかしくって、ほかの誰かを推したてようしてる連中もたくさんいる。ぼくはそいつらを尊敬する。これは君の選択なんだ。ぶつくさ不平を言うことはメニューにはないんだよ。さあ、寝る時間だ。そうじゃなきゃ自分の案をポストしろよ。」
ウィルはゆっくりと体を起こすと、枕として使っていたジャケットを広げ、着込んだ。
「ばかなお二人さん、ぼくはここを出るよ。」
「ぜったいここを離れないと思ったんだけどな」
フェリックスはそう言うと寝返りを打った。眠れなかった。選挙について考えていた。
ほかにも稼働しているものがいた。中にはシスアドでさえない者もいた。ワイオミの夏用別荘に避難していた合衆国上院議員で自家発電機と衛星電話を持っていたのだ。彼はどういうわけか正しくこのニュースグループを見つけて立候補したのだった。イタリアの無政府主義ハッカーは一晩中、怪しげな英語の長文で新世界での「政府」という政治的破産ついてポストして、このニュースグループを攻撃していた。フェリックスは彼らのネットワークIPを確認すると、彼らがトリノ近くの小さなInteraction Design instituteにいることを確認した。イタリアは壊滅的だったが、小さな町は生き残ったのだ。この無政府主義者達は反抗を選んだのだ。
驚くべき数のマシンがインターネットをシャットダウンすることについてのニュースグループに参加していた。フェリックスはそれが果して可能なのか疑っていた。 しかし、彼はインターネットをシャットダウンすることが、復旧作業を終了させ、世界をも終了させるような衝撃だと感じていた。 なぜ? すべてか指し示すもの。そのことは一連のディザスター、攻撃、日和見主義から破滅への一歩だと思えた。 テロリストはここを攻撃し、過剰な反応を起こした政府からのカウンター攻撃... すぐに世界のthey'd made short work of the world.
彼はインターネットをシャットダウンさせる方法について考えているうちに眠りおちた。そして夢を見た。彼がネットワークの唯一の保守者になる悪夢だった。
彼はカサカサいう紙のような落ち着かない音で目が覚めた。寝返りを打つとヴァンが上体を起こしているのが見えた。彼は上着をひじのところまでまくりあげると、必死に細い腕をかいていた。コーンビーフのような色になり、ひどいありさまだった。カフェテリアの窓から差し込んでくる光で皮膚の破片が雲のように舞い上がっているのが見えた。
「なにやってるんだ。」
フェリックスは起き上がると。ヴァンの指の爪が肌に食い込むのを見るとフィリックスまでかゆみを感じた。ヴァンが最後に頭を洗ったのは3日前だった。まるで卵を産む虫がわざわざ彼の頭を選んで住みついているように感じられていた。 ヴァンは昨夜メガネを調整していた。そして耳の後ろを触った。彼の指は分厚い油分で光っていた。彼は2、3日シャワーを浴びないと耳の後ろに吹き出物ができるのだった。そしてときには巨大で根の深いなはれものがケロイド状になり強烈な臭いを発するのだった。
「掻いてんだよ。」
彼はそう言うと頭に取りかかった。フケの雲が舞い上がり、彼の頭頂のすでに引き剥がしたフケに加わった。
「くそっ。もうそこらじゅうがかゆいんだよ。」
フェリックスはマックチーズ市長をヴァンのバックパックから取り出すと、床じゅうにへびのように這っているイーサネットケーブルをプラグへ差し込んだ。 彼はグーグルでヴァンの症状に関する考えられるすべての単語を検索した。「かゆみ」には40,600,000のリンクが表示された。彼は対象を絞ろうとさらに検索単語を追加した。
「たぶんストレス性の湿疹だ。」
フェリックスは検索結果から答えた。
「湿疹なんかじゃない。」
ヴァンがそう言うと、 フェリックスは彼にぞっとする赤く腫れ上がった肌、白くかさかさになった皮膚の写真を見せた。
「ストレス性の湿疹」
フェリックスは写真についたキャプションを声に出して読んだ。
ヴァンは自分の腕を丹念に調べ、言った。
「湿疹だ。」
「ここに書いてある。保湿コルチゾンクリームを塗ってください。2階のトイレにある救急セットにあるかも。たしかあったはずだ。」
多くのシスアドと同様に、フェリックスはオフィスとトイレ、台所や倉庫をくまなく探して、ショルダーバッグにトイレットペーパーをパワーバーと一緒にしまいこんでいた。 暗黙の了解としてカフェテリアでは食べ物を分け合っていたが、みんな誰かが大食いしていないか、貯め込んでいないかを見張っていた。 みんな食糧の貯め込み、飲食がおこなわれていることを知っていた。みんなそのことで罪の意識を感じていたのだから。
ヴァンは起き上がり顔を照明の方に向けると、フィリックスは彼の目が充血しているのがわかった。 「メーリングリストに抗ヒスタミン剤をたのんどくよ」 生存者により作成された4つのメーリングリストと3つのWikiが最初のミーティングのあとすぐ作成されたが、数日が過ぎた現在では1つに落ち着いていた。 フィリックスは彼の頼りになる5人の友人とのメーリングリストにも参加していたが、そのなかの2人は別の国のケージの中にいた。 彼は他の場所のシスアド達も同じように過ごしているだろうと考えていた。
ヴァンはよろめきながら立ち上がると、「選挙がんばれよな」とフィリックスの肩をたたいた。
フィリックスは立ち上がるり、よごれた窓へ駆け寄るとの外を見た。トロントではまだ火が消えておらず、むしろ勢いを増しているようだった。 彼はトロントの誰かがメーリングリストかブログにポストしていないか確かめ たが、見つけることができたのは別のデータセンターでほかの技術者により運 用されているものだった。生存者の中にはメーリングリストやブログに投稿す るよりも大事なことがあるのはあ当然だったし、そのほうがありそうなこと だった。彼の家の電話は2回に1回はまだ動いていたが、二日目には電話するこ とを止めていた。ボイスメールのケーリの声を50回目に聴いたときには、彼は ミーティング中にもかかわらず泣いた。彼一人ではなかった。
投票日。自ら選んだ結果なのだ。
> 緊張してる?
> いいや。
フィリックスはタイプすると続けた。
> 正直いうと、ぼくが勝つかは気にしてないんだ。ぼくはただぼくらが選挙をお > こなったことがうれしいんだ。これをしなきゃ、誰かがドアを外から開けて > くれるのを待ってるしかなかったから。
カーソルがハングした。クイーンコングはフル稼働でグーグルサーバ群で自らのグーグロイドを指 揮し彼女のデータセンターを落さないよう必死だった。海外にあるケージある グーグルサーバのうち3つが落ち、6つ冗長ネットワークのうち2つのネットワー ク・リンクが悲鳴をあげていた。幸運なことに1秒間のクエリ数は落ち込んで いた。
> 中国はまだある。
she typed. Queen Kong had a big board with a map of the world colored in Google-queries-per-second, and could do magic with it, showing the drop-off over time in colorful charts. She'd uploaded lots of video clips showing how the plague and the bombs had swept the world: the initial upswell of queries from people wanting to find out what was going on, then the grim, precipitous shelving off as the plagues took hold.
> China's still running about ninety percent nominal.
Felix shook his head.
> You can't think that they're responsible
> No
she typed, but then she started to key something and then stopped.
> No of course not. I believe the Popovich Hypothesis. Every asshole in the world is using the other assholes for cover. But China put them down harder and faster than anyone else. Maybe we've finally found a use for totalitarian states.
Felix couldn't resist. He typed:
> You're lucky your boss can't see you type that. You guys were pretty enthusiastic participants in the Great Firewall of China.
> Wasn't my idea
she typed.
> And my boss is dead. They're probably all dead. The whole Bay Area got hit hard, and then there was the quake.
They'd watched the USGS's automated data-stream from the 6.9 that trashed northern Cal from Gilroy to Sebastapol. Soma webcams revealed the scope of the damage—gas main explosions, seismically retrofitted buildings crumpling like piles of children's blocks after a good kicking. The Googleplex, floating on a series of gigantic steel springs, had shook like a plateful of jello, but the racks had stayed in place and the worst injury they'd had was a badly bruised eye on a sysadmin who'd caught a flying cable-crimper in the face.
> Sorry. I forgot.
> It's OK. We all lost people, right?
> Yeah. Yeah. Anyway, I'm not worried about the election. Whoever wins, at least we're doing SOMETHING
> Not if they vote for one of the fuckrags
Fuckrag was the epithet that some of the sysadmins were using to describe the contingent that wanted to shut down the Internet. Queen Kong had coined it—apparently it had started life as a catch-all term to describe clueless IT managers that she'd chewed up through her career.
> They won't. They're just tired and sad is all. Your endorsement will carry the day
The Googloids were one of the largest and most powerful blocs left behind, along with the satellite uplink crews and the remaining transoceanic crews. Queen Kong's endorsement had come as a surprise and he'd sent her an email that she'd replied to tersely: “can't have the fuckrags in charge.”
> gtg
she typed and then her connection dropped. He fired up a browser and called up google.com. The browser timed out. He hit reload, and then again, and then the Google front-page came back up. Whatever had hit Queen Kong's workplace—power failure, worms, another quake—she had fixed it. He snorted when he saw that they'd replaced the O's in the Google logo with little planet Earths with mushroom clouds rising from them.
第九
“Got anything to eat?” Van said to him. It was mid-afternoon, not that time particularly passed in the data-center. Felix patted his pockets. They'd put a quartermaster in charge, but not before everyone had snagged some chow out of the machines. He'd had a dozen power-bars and some apples. He'd taken a couple sandwiches but had wisely eaten them first before they got stale.
“One power-bar left,” he said. He'd noticed a certain looseness in his waistline that morning and had briefly relished it. Then he'd remembered Kelly's teasing about his weight and he'd cried some. Then he'd eaten two power bars, leaving him with just one left.
“Oh,” Van said. His face was hollower than ever, his shoulders sloping in on his toast-rack chest.
“Here,” Felix said. “Vote Felix.”
Van took the power-bar from him and then put it down on the table. “OK, I want to give this back to you and say, 'No, I couldn't,' but I'm fucking hungry, so I'm just going to take it and eat it, OK?”
“That's fine by me,” Felix said. “Enjoy.”
“How are the elections coming?” Van said, once he'd licked the wrapper clean.
“Dunno,” Felix said. “Haven't checked in a while.” He'd been winning by a slim margin a few hours before. Not having his laptop was a major handicap when it came to stuff like this. Up in the cages, there were a dozen more like him, poor bastards who'd left the house on Der Tag without thinking to snag something WiFi-enabled.
“You're going to get smoked,” Sario said, sliding in next to them. He'd become famous in the center for never sleeping, for eavesdropping, for picking fights in RL that had the ill-considered heat of a Usenet flamewar. “The winner will be someone who understands a couple of fundamental facts.” He held up a fist, then ticked off his bullet points by raising a finger at a time. “Point: The terrorists are using the Internet to destroy the world, and we need to destroy the Internet first. Point: Even if I'm wrong, the whole thing is a joke. We'll run out of generator-fuel soon enough. Point: Or if we don't, it will be because the old world will be back and running, and it won't give a crap about your new world. Point: We're gonna run out of food before we run out of shit to argue about or reasons not to go outside. We have the chance to do something to help the world recover: we can kill the net and cut it off as a tool for bad guys. Or we can rearrange some more deck chairs on the bridge of your personal Titanic in the service of some sweet dream about an 'independent cyberspace.'”
The thing was that Sario was right. They would be out of fuel in two days—intermittent power from the grid had stretched their generator lifespan. And if you bought his hypothesis that the Internet was primarily being used as a tool to organize more mayhem, shutting it down would be the right thing to do.
But Felix's son and his wife were dead. He didn't want to rebuild the old world. He wanted a new one. The old world was one that didn't have any place for him. Not anymore.
Van scratched his raw, flaking skin. Puffs of dander and scurf swirled in the musty, greasy air. Sario curled a lip at him. “That is disgusting. We're breathing recycled air, you know. Whatever leprosy is eating you, aerosolizing it into the air supply is pretty anti-social.”
“You're the world's leading authority on anti-social, Sario,” Van said. “Go away or I'll multi-tool you to death.” He stopped scratching and patted his sheathed multi-pliers like a gunslinger.
“Yeah, I'm anti-social. I've got Asperger's and I haven't taken any meds in four days. What's your fucking excuse.”
Van scratched some more. “I'm sorry,” he said. “I didn't know.”
Sario cracked up. “Oh, you are priceless. I'd bet that three quarters of this bunch is borderline autistic. Me, I'm just an asshole. But I'm one who isn't afraid to tell the truth, and that makes me better than you, dickweed.”
“Fuckrag,” Felix said, “fuck off.”
第十
They had less than a day's worth of fuel when Felix was elected the first ever Prime Minister of Cyberspace. The first count was spoiled by a bot that spammed the voting process and they lost a critical day while they added up the votes a second time.
But by then, it was all seeming like more of a joke. Half the data-centers had gone dark. Queen Kong's net-maps of Google queries were looking grimmer and grimmer as more of the world went offline, though she maintained a leader-board of new and rising queries—largely related to health, shelter, sanitation and self-defense.
Worm-load slowed. Power was going off to many home PC users, and staying off, so their compromised PCs were going dark. The backbones were still lit up and blinking, but the missives from those data-centers were looking more and more desperate. Felix hadn't eaten in a day and neither had anyone in a satellite Earth-station of transoceanic head-end.
Water was running short, too.
Popovich and Rosenbaum came and got him before he could do more than answer a few congratulatory messages and post a canned acceptance speech to newsgroups.
“We're going to open the doors,” Popovich said. Like all of them, he'd lost weight and waxed scruffy and oily. His BO was like a cloud coming off a trash-bags behind a fish-market on a sunny day. Felix was quite sure he smelled no better.
“You're going to go for a reccy? Get more fuel? We can charter a working group for it—great idea.”
Rosenbaum shook his head sadly. “We're going to go find our families. Whatever is out there has burned itself out. Or it hasn't. Either way, there's no future in here.”
“What about network maintenance?” Felix said, thought he knew the answers. “Who'll keep the routers up?”
“We'll give you the root passwords to everything,” Popovich said. His hands were shaking and his eyes were bleary. Like many of the smokers stuck in the data-center, he'd gone cold turkey this week. They'd run out of caffeine products two days earlier, too. The smokers had it rough.
“And I'll just stay here and keep everything online?”
“You and anyone else who cares anymore.”
Felix knew that he'd squandered his opportunity. The election had seemed noble and brave, but in hindsight all it had been was an excuse for infighting when they should have been figuring out what to do next. The problem was that there was nothing to do next.
“I can't make you stay,” he said.
“Yeah, you can't.” Popovich turned on his heel and walked out. Rosenbaum watched him go, then he gripped Felix's shoulder and squeezed it.
“Thank you, Felix. It was a beautiful dream. It still is. Maybe we'll find something to eat and some fuel and come back.”
Rosenbaum had a sister whom he'd been in contact with over IM for the first days after the crisis broke. Then she'd stopped answering. The sysadmins were split among those who'd had a chance to say goodbye and those who hadn't. Each was sure the other had it better.
They posted about it on the internal newsgroup—they were still geeks, after all, and there was a little honor guard on the ground floor, geeks who watched them pass toward the double doors. They manipulated the keypads and the steel shutters lifted, then the first set of doors opened. They stepped into the vestibule and pulled the doors shut behind them. The front doors opened. It was very bright and sunny outside, and apart from how empty it was, it looked very normal. Heartbreakingly so.
The two took a tentative step out into the world. Then another. They turned to wave at the assembled masses. Then they both grabbed their throats and began to jerk and twitch, crumpling in a heap on the ground.
“Shiii—!” was all Felix managed to choke out before they both dusted themselves off and stood up, laughing so hard they were clutching their sides. They waved once more and turned on their heels.
“Man, those guys are sick,” Van said. He scratched his arms, which had long, bloody scratches on them. His clothes were so covered in scurf they looked like they'd been dusted with icing sugar.
“I thought it was pretty funny,” Felix said.
“Christ I'm hungry,” Van said, conversationally.
“Lucky for you, we've got all the packets we can eat,” Felix said.
“You're too good to us grunts, Mr President,” Van said.
“Prime Minister,” he said. “And you're no grunt, you're the Deputy Prime Minister. You're my designated ribbon-cutter and hander-out of oversized novelty checks.”
It buoyed both of their spirits. Watching Popovich and Rosenbaum go, it buoyed them up. Felix knew then that they'd all be going soon.
That had been pre-ordained by the fuel-supply, but who wanted to wait for the fuel to run out, anyway?
第十一
> half my crew split this morning
Queen Kong typed. Google was holding up pretty good anyway, of course. The load on the servers was a lot lighter than it had been since the days when Google fit on a bunch of hand-built PCs under a desk at Stanford.
> we're down to a quarter
Felix typed back. It was only a day since Popovich and Rosenbaum left, but the traffic on the newsgroups had fallen down to near zero. He and Van hadn't had much time to play Republic of Cyberspace. They'd been too busy learning the systems that Popovich had turned over to them, the big, big routers that had went on acting as the major interchange for all the network backbones in Canada.
Still, someone posted to the newsgroups every now and again, generally to say goodbye. The old flamewars about who would be PM, or whether they would shut down the network, or who took too much food—it was all gone.
He reloaded the newsgroup. There was a typical message.
> Runaway processes on Solaris TK
>
> Uh, hi. I'm just a lightweight MSCE but I'm the only one awake here and four of the DSLAMs just went down. Looks like there's some custom accounting code that's trying to figure out how much to bill our corporate customers and it's spawned ten thousand threads and its eating all the swap. I just want to kill it but I can't seem to do that. Is there some magic invocation I need to do to get this goddamned weenix box to kill this shit? I mean, it's not as if any of our customers are ever going to pay us again. I'd ask the guy who wrote this code, but he's pretty much dead as far as anyone can work out.
He reloaded. There was a response. It was short, authoritative, and helpful—just the sort of thing you almost never saw in a high-caliber newsgroup when a noob posted a dumb question. The apocalypse had awoken the spirit of patient helpfulness in the world's sysop community.
Van shoulder-surfed him. “Holy shit, who knew he had it in him?”
He looked at the message again. It was from Will Sario.
He dropped into his chat window.
> sario i thought you wanted the network dead why are you helping msces fix their boxen?
> Gee Mr PM, maybe I just can't bear to watch a computer suffer at the hands of an amateur.
He flipped to the channel with Queen Kong in it.
> How long?
> Since I slept? Two days. Until we run out of fuel? Three days. Since we ran out of food? Two days.
> Jeez. I didn't sleep last night either. We're a little short handed around here.
> asl? Im monica and I live in pasadena and Im bored with my homework. WOuld you like to download my pic???
The trojan bots were all over IRC these days, jumping to every channel that had any traffic on it. Sometimes you caught five or six flirting with each other. It was pretty weird to watch a piece of malware try to con another instance of itself into downloading a trojan.
They both kicked the bot off the channel simultaneously. He had a script for it now. The spam hadn't even tailed off a little.
> How come the spam isn't reducing? Half the goddamned data-centers have gone dark
Queen Kong paused a long time before typing. As had become automatic when she went high-latency, he reloaded the Google homepage. Sure enough, it was down.
> Sario, you got any food?
> You won't miss a couple more meals, Your Excellency
Van had gone back to Mayor McCheese but he was in the same channel.
“What a dick. You're looking pretty buff, though, dude.”
Van didn't look so good. He looked like you could knock him over with a stiff breeze and he had a phlegmy, weak quality to his speech.
> hey kong everything ok?
> everything's fine just had to go kick some ass
“How's the traffic, Van?”
“Down 25 percent from this morning,” he said. There were a bunch of nodes whose connections routed through them. Presumably most of these were home or commercial customers in places where the power was still on and the phone company's COs were still alive.
Every once in a while, Felix would wiretap the connections to see if he could find a person who had news of the wide world. Almost all of it was automated traffic, though: network backups, status updates. Spam. Lots of spam.
> Spam's still up because the services that stop spam are failing faster than the services that create it. All the anti-worm stuff is centralized in a couple places. The bad stuff is on a million zombie computers. If only the lusers had had the good sense to turn off their home PCs before keeling over or taking off
> at the rate were going well be routing nothing but spam by dinnertime
Van cleared his throat, a painful sound. “About that,” he said. “I think it's going to hit sooner than that. Felix, I don't think anyone would notice if we just walked away from here.”
Felix looked at him, his skin the color of corned-beef and streaked with long, angry scabs. His fingers trembled.
“You drinking enough water?”
Van nodded. “All frigging day, every ten seconds. Anything to keep my belly full.” He pointed to a refilled Pepsi Max bottle full of water by his side.
“Let's have a meeting,” he said.
第十二
There had been forty-three of them on D-Day. Now there were fifteen. Six had responded to the call for a meeting by simply leaving. Everyone knew without having to be told what the meeting was about.
“So that's it, you're going to let it all fall apart?” Sario was the only one with the energy left to get properly angry. He'd go angry to his grave. The veins on his throat and forehead stood out angrily. His fists shook angrily. All the other geeks went lids-down at the site of him, looking up in unison for once at the discussion, not keeping one eye on a chat-log or a tailed service log.
“Sario, you've got to be shitting me,” Felix said. “You wanted to pull the goddamned plug!”
“I wanted it to go clean,” he shouted. “I didn't want it to bleed out and keel over in little gasps and pukes forever. I wanted it to be an act of will by the global community of its caretakers. I wanted it to be an affirmative act by human hands. Not entropy and bad code and worms winning out. Fuck that, that's just what's happened out there.”
Up in the top-floor cafeteria, there were windows all around, hardened and light-bending, and by custom, they were all blinds-down. Now Sario ran around the room, yanking down the blinds. How the hell can he get the energy to run? Felix wondered. He could barely walk up the stairs to the meeting room.
Harsh daylight flooded in. It was a fine sunny day out there, but everywhere you looked across that commanding view of Toronto's skyline, there were rising plumes of smoke. The TD tower, a gigantic black modernist glass brick, was gouting flame to the sky. "It's all falling apart, the way everything does.
“Listen, listen. If we leave the network to fall over slowly, parts of it will stay online for months. Maybe years. And what will run on it? Malware. Worms. Spam. System-processes. Zone transfers. The things we use fall apart and require constant maintenance. The things we abandon don't get used and they last forever. We're going to leave the network behind like a lime-pit filled with industrial waste. That will be our fucking legacy—the legacy of every keystroke you and I and anyone, anywhere ever typed. You understand? We're going to leave it to die slow like a wounded dog, instead of giving it one clean shot through the head.”
Van scratched his cheeks, then Felix saw that he was wiping away tears.
“Sario, you're not wrong, but you're not right either,” he said. “Leaving it up to limp along is right. We're going to all be limping for a long time, and maybe it will be some use to someone. If there's one packet being routed from any user to any other user, anywhere in the world, it's doing its job.”
“If you want a clean kill, you can do that,” Felix said. “I'm the PM and I say so. I'm giving you root. All of you.” He turned to the white-board where the cafeteria workers used to scrawl the day's specials. Now it was covered with the remnants of heated technical debates that the sysadmins had engaged in over the days since the day.
He scrubbed away a clean spot with his sleeve and began to write out long, complicated alphanumeric passwords salted with punctuation. Felix had a gift for remembering that kind of password. He doubted it would do him much good, ever again.
第十三
> Were going, kong. Fuels almost out anyway
> yeah well thats right then. it was an honor, mr prime minister
> you going to be ok?
> ive commandeered a young sysadmin to see to my feminine needs and weve found another cache of food thatll last us a coupel weeks now that were down to fifteen admins—im in hog heaven pal
> youre amazing, Queen Kong, seriously. Dont be a hero though. When you need to go go. Theres got to be something out there
> be safe felix, seriously—btw did i tell you queries are up in Romania? maybe theyre getting back on their feet
> really?
> yeah, really. we're hard to kill—like fucking roaches
Her connection died. He dropped to Firefox and reloaded Google and it was down. He hit reload and hit reload and hit reload, but it didn't come up. He closed his eyes and listened to Van scratch his legs and then heard Van type a little.
“They're back up,” he said.
Felix whooshed out a breath. He sent the message to the newsgroup, one that he'd run through five drafts before settling on, “Take care of the place, OK? We'll be back, someday.”
Everyone was going except Sario. Sario wouldn't leave. He came down to see them off, though.
The sysadmins gathered in the lobby and Felix made the safety door go up, and the light rushed in.
Sario stuck his hand out.
“Good luck,” he said.
“You too,” Felix said. He had a firm grip, Sario, stronger than he had any right to be. “Maybe you were right,” he said.
“Maybe,” he said.
“You going to pull the plug?”
Sario looked up at the drop-ceiling, seeming to peer through the reinforced floors at the humming racks above. “Who knows?” he said at last.
Van scratched and a flurry of white motes danced in the sunlight.
“Let's go find you a pharmacy,” Felix said. He walked to the door and the other sysadmins followed.
They waited for the interior doors to close behind them and then Felix opened the exterior doors. The air smelled and tasted like a mown grass, like the first drops of rain, like the lake and the sky, like the outdoors and the world, an old friend not heard from in an eternity.
“Bye, Felix,” the other sysadmins said. They were drifting away while he stood transfixed at the top of the short concrete staircase. The light hurt his eyes and made them water.
“I think there's a Shopper's Drug Mart on King Street,” he said to Van. “We'll throw a brick through the window and get you some cortisone, OK?”
“You're the Prime Minister,” Van said. “Lead on.”
第十四
They didn't see a single soul on the fifteen minute walk. There wasn't a single sound except for some bird noises and some distant groans, and the wind in the electric cables overhead. It was like walking on the surface of the moon.
“Bet they have chocolate bars at the Shopper's,” Van said.
Felix's stomach lurched. Food. “Wow,” he said, around a mouthful of saliva.
They walked past a little hatchback and in the front seat was the dried body of a woman holding the dried body of a baby, and his mouth filled with sour bile, even though the smell was faint through the rolled-up windows.
He hadn't thought of Kelly or 2.0 in days. He dropped to his knees and retched again. Out here in the real world, his family was dead. Everyone he knew was dead. He just wanted to lie down on the sidewalk and wait to die, too.
Van's rough hands slipped under his armpits and hauled weakly at him. “Not now,” he said. “Once we're safe inside somewhere and we've eaten something, then and then you can do this, but not now. Understand me, Felix? Not fucking now.”
The profanity got through to him. He got to his feet. His knees were trembling.
“Just a block more,” Van said, and slipped Felix's arm around his shoulders and led him along.
“Thank you, Van. I'm sorry.”
“No sweat,” he said. “You need a shower, bad. No offense.”
“None taken.”
The Shoppers had a metal security gate, but it had been torn away from the front windows, which had been rudely smashed. Felix and Van squeezed through the gap and stepped into the dim drug-store. A few of the displays were knocked over, but other than that, it looked OK. By the cash-registers, Felix spotted the racks of candy bars at the same instant that Van saw them, and they hurried over and grabbed a handful each, stuffing their faces.
“You two eat like pigs.”
They both whirled at the sound of the woman's voice. She was holding a fire-axe that was nearly as big as she was. She wore a lab-coat and comfortable shoes.
“You take what you need and go, OK? No sense in there being any trouble.” Her chin was pointy and her eyes were sharp. She looked to be in her forties. She looked nothing like Kelly, which was good, because Felix felt like running and giving her a hug as it was. Another person alive!
“Are you a doctor?” Felix said. She was wearing scrubs under the coat, he saw.
“You going to go?” She brandished the axe.
Felix held his hands up. “Seriously, are you a doctor? A pharmacist?”
“I used to be a RN, ten years ago. I'm mostly a Web-designer.”
“You're shitting me,” Felix said.
“Haven't you ever met a girl who knew about computers?”
“Actually, a friend of mine who runs Google's data-center is a girl. A woman, I mean.”
“You're shitting me,” she said. “A woman ran Google's data-center?”
“Runs,” Felix said. “It's still online.”
“NFW,” she said. She let the axe lower.
“Way. Have you got any cortisone cream? I can tell you the story. My name's Felix and this is Van, who needs any anti-histamines you can spare.”
“I can spare? Felix old pal, I have enough dope here to last a hundred years. This stuff's going to expire long before it runs out. But are you telling me that the net's still up?”
“It's still up,” he said. “Kind of. That's what we've been doing all week. Keeping it online. It might not last much longer, though.”
“No,” she said. “I don't suppose it would.” She set the axe down. “Have you got anything to trade? I don't need much, but I've been trying to keep my spirits up by trading with the neighbors. It's like playing civilization.”
“You have neighbors?”
“At least ten,” she said. “The people in the restaurant across the way make a pretty good soup, even if most of the veg is canned. They cleaned me out of Sterno, though.”
“You've got neighbors and you trade with them?”
“Well, nominally. It'd be pretty lonely without them. I've taken care of whatever sniffles I could. Set a bone—broken wrist. Listen, do you want some Wonder Bread and peanut butter? I have a ton of it. Your friend looks like he could use a meal.”
“Yes please,” Van said. “We don't have anything to trade, but we're both committed workaholics looking to learn a trade. Could you use some assistants?”
“Not really.” She spun her axe on its head. “But I wouldn't mind some company.”
They ate the sandwiches and then some soup. The restaurant people brought it over and made their manners at them, though Felix saw their noses wrinkle up and ascertained that there was working plumbing in the back room. Van went in to take a sponge bath and then he followed.
“None of us know what to do,” the woman said. Her name was Rosa, and she had found them a bottle of wine and some disposable plastic cups from the housewares aisle. “I thought we'd have helicopters or tanks or even looters, but it's just quiet.”
“You seem to have kept pretty quiet yourself,” Felix said.
“Didn't want to attract the wrong kind of attention.”
“You ever think that maybe there's a lot of people out there doing the same thing? Maybe if we all get together we'll come up with something to do.”
“Or maybe they'll cut our throats,” she said.
Van nodded. “She's got a point.”
Felix was on his feet. “No way, we can't think like that. Lady, we're at a critical juncture here. We can go down through negligence, dwindling away in our hiding holes, or we can try to build something better.”
“Better?” She made a rude noise.
“OK, not better. Something though. Building something new is better than letting it dwindle away. Christ, what are you going to do when you've read all the magazines and eaten all the potato chips here?”
Rosa shook her head. “Pretty talk,” she said. “But what the hell are we going to do, anyway?”
“Something,” Felix said. “We're going to do something. Something is better than nothing. We're going to take this patch of the world where people are talking to each other, and we're going to expand it. We're going to find everyone we can and we're going to take care of them and they're going to take care of us. We'll probably fuck it up. We'll probably fail. I'd rather fail than give up, though.”
Van laughed. “Felix, you are crazier than Sario, you know it?”
“We're going to go and drag him out, first thing tomorrow. He's going to be a part of this, too. Everyone will. Screw the end of the world. The world doesn't end. Humans aren't the kind of things that have endings.”
Rosa shook her head again, but she was smiling a little now. “And you'll be what, the Pope-Emperor of the World?”
“He prefers Prime Minister,” Van said in a stagey whisper. The anti-histamines had worked miracles on his skin, and it had faded from angry red to a fine pink.
“You want to be Minister of Health, Rosa?” he said.
“Boys,” she said. “Playing games. How about this. I'll help out however I can, provided you never ask me to call you Prime Minister and you never call me the Minister of Health?”
“It's a deal,” he said.
Van refilled their glasses, upending the wine bottle to get the last few drops out.
They raised their glasses. “To the world,” Felix said. “To humanity.” He thought hard. “To rebuilding.”
“To anything,” Van said.
“To anything,” Felix said. “To everything.”
“To everything,” Rosa said.
They drank. He wanted to go see the house—see Kelly and 2.0, though his stomach churned at the thought of what he might find there. But the next day, they started to rebuild. And months later, they started over again, when disagreements drove apart the fragile little group they'd pulled together. And a year after that, they started over again. And five years later, they started again.
It was nearly six months before he went home. Van helped him along, riding cover behind him on the bicycles they used to get around town. The further north they rode, the stronger the smell of burnt wood became. There were lots of burnt-out houses. Sometimes marauders burnt the houses they'd looted, but more often it was just nature, the kinds of fires you got in forests and on mountains. There were six choking, burnt blocks where every house was burnt before they reached home.
But Felix's old housing development was still standing, an oasis of eerily pristine buildings that looked like maybe their somewhat neglectful owners had merely stepped out to buy some paint and fresh lawnmower blades to bring their old homes back up to their neat, groomed selves.
That was worse, somehow. He got off the bike at the entry of the subdivision and they walked the bikes together in silence, listening to the sough of the wind in the trees. Winter was coming late that year, but it was coming, and as the sweat dried in the wind, Felix started to shiver.
He didn't have his keys anymore. They were at the data-center, months and worlds away. He tried the door-handle, but it didn't turn. He applied his shoulder to the door and it ripped away from its wet, rotted jamb with a loud, splintering sound. The house was rotting from the inside.
The door splashed when it landed. The house was full of stagnant water, four inches of stinking pond-scummed water in the living room. He splashed carefully through it, feeling the floor-boards sag spongily beneath each step.
Up the stairs, his nose full of that terrible green mildewy stench. Into the bedroom, the furniture familiar as a childhood friend.
Kelly was in the bed with 2.0. The way they both lay, it was clear they hadn't gone easy—they were twisted double, Kelly curled around 2.0. Their skin was bloated, making them almost unrecognizable. The smell—God, the smell.
Felix's head spun. He thought he would fall over and clutched at the dresser. An emotion he couldn't name—rage, anger, sorrow?—made him breathe hard, gulp for air like he was drowning.
And then it was over. The world was over. Kelly and 2.0—over. And he had a job to do. He folded the blanket over them—Van helped, solemnly. They went into the front yard and took turns digging, using the shovel from the garage that Kelly had used for gardening. They had lots of experience digging graves by then. Lots of experience handling the dead. They dug, and wary dogs watched them from the tall grass on the neighboring lawns, but they were also good at chasing off dogs with well-thrown stones.
When the grave was dug, they laid Felix's wife and son to rest in it. Felix quested after words to say over the mound, but none came. He'd dug so many graves for so many men's wives and so many women's husbands and so many children—the words were long gone.
Felix dug ditches and salvaged cans and buried the dead. He planted and harvested. He fixed some cars and learned to make biodiesel. Finally he fetched up in a data-center for a little government—little governments came and went, but this one was smart enough to want to keep records and needed someone to keep everything running, and Van went with him.
They spent a lot of time in chat rooms and sometimes they happened upon old friends from the strange time they'd spent running the Distributed Republic of Cyberspace, geeks who insisted on calling him PM, though no one in the real world ever called him that anymore.
It wasn't a good life, most of the time. Felix's wounds never healed, and neither did most other people's. There were lingering sicknesses and sudden ones. Tragedy on tragedy.
But Felix liked his data-center. There in the humming of the racks, he never felt like it was the first days of a better nation, but he never felt like it was the last days of one, either.
> go to bed, felix
> soon, kong, soon—almost got this backup running
> youre a junkie, dude.
> look whos talking
He reloaded the Google homepage. Queen Kong had had it online for a couple years now. The Os in Google changed all the time, whenever she got the urge. Today they were little cartoon globes, one smiling the other frowning.
He looked at it for a long time and dropped back into a terminal to check his backup. It was running clean, for a change. The little government's records were safe.
> ok night night
> take care
Van waved at him as he creaked to the door, stretching out his back with a long series of pops.
“Sleep well, boss,” he said.
“Don't stick around here all night again,” Felix said. “You need your sleep, too.”
“You're too good to us grunts,” Van said, and went back to typing.
Felix went to the door and walked out into the night. Behind him, the biodiesel generator hummed and made its acrid fumes. The harvest moon was up, which he loved. Tomorrow, he'd go back and fix another computer and fight off entropy again. And why not?
It was what he did. He was a sysadmin. [edit]
他の記事
- Translations:When Sysadmins Ruled the Earth:en
- Translations:When Sysadmins Ruled the Earth:fr
- Translations:When Sysadmins Ruled the Earth:ja
- Translations:When Sysadmins Ruled the Earth:vi
Category:Translations

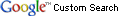
 /
/